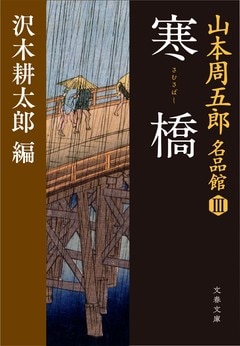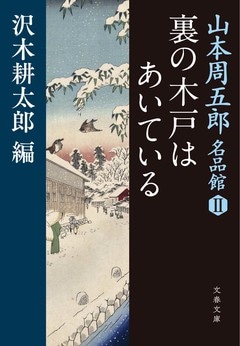ひとりの作家が、文学の高みを目指すのではなく、読者に受け入れられる世界をひたすら再生産していこうと思い決める契機とはどのようなものなのだろう、と私は思ったのだ。
その山手樹一郎の「断念の契機」については、のちに、山本周五郎がこう語っているのを知って、なるほどと思った。
井口が作家として立つため博文館をやめるのを知って、山本周五郎は自分の住む大森馬込の文士村に引っ越してきて、一緒にやっていかないかと勧めた。すると、井口はこう言って断ったという。
「自分は家族を大勢かかえて裸を覚悟ではじめるのだから、明日紙屑になってしまうものでも生活のために原稿を書いて行かなきゃならないんで、つまり慣れた仕事でやって行くほかはない、そっちの仲間に入るのは勘弁してくれ」
ここに山手樹一郎の「断念」の根があったのだ。
そのやりとりの詳細が記されているのは、山本周五郎の「畏友山手樹一郎へ」という談話においてである。
昭和三十五年、三世社が「時代傑作小説」という雑誌の増刊号として『山手樹一郎・山本周五郎――小説読本――』という、今風に言えばムックのような出版物を企画した。
そこで、その編集者は面白いことを考えた。二人に、往復書簡ならぬ、往復テープを録音させ、相互に聞かせるということをしたのだ。