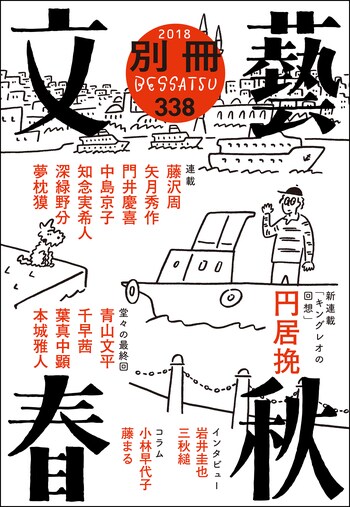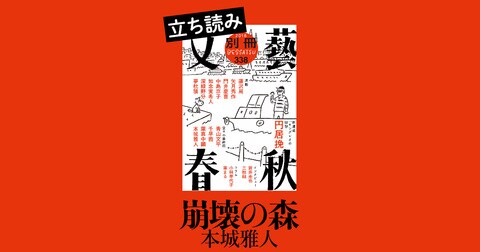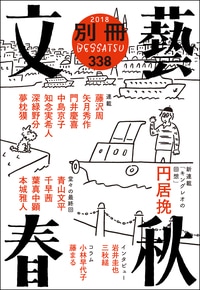
その能の路を、いま鵺で締め括ろうとしている。
どうにも行き場のない三日を、野宮の役者にくれてやるのはどうか。
生きていくだけでいっぱいで、己れが何者であるかなど考えたこともなかった。
だから、己れをなにに仮託してよいのかわからない。
曲を勤めるときも、努めてシテに己れを重ねることなく、いまから振り返れば、軸だけで舞ってきた。
でも、鵺は化生の者だ。
妖怪であり、鬼だ。
頭は猿で、手足は虎で、尾は蛇で、鳴く声は夜の深い森に物哀しい口笛のように響き渡る虎鶫だ。
つまりは、鵺は猿ではない。
虎でもない。
蛇でも、虎鶫でもない。
鵺は誰でもない。
誰でもない鵺なら、己れでもいい。
鵺なら己れを重ねることができる。
はたしてそんなことができるのかどうかはわからぬが、剛は鵺を軸ではなく、己れで舞おうと思った。
軸の節理は置く。己れの節理で舞う。
だから、この三日、鵺になる。
そうと思い立った剛は、夕刻を待って、又四郎を呼んだ。
「想いも寄らぬこと」を伝えるためではない。
あの都鳥の名処がある今戸町へ向かうために呼んだ。
この前は姿が見えなかったが、都鳥は冬鳥だという。師走のいまならば渡り来ているだろうが、月の光には浮かび上がるまい。火事と見紛う黒煙を放つ瓦の窯だって、これから向かうのであれば火を落としているだろうし、西の風が運ぶ仕置場の臭いもきっと届かぬかもしれない。