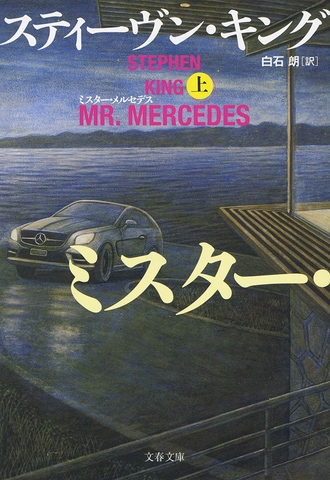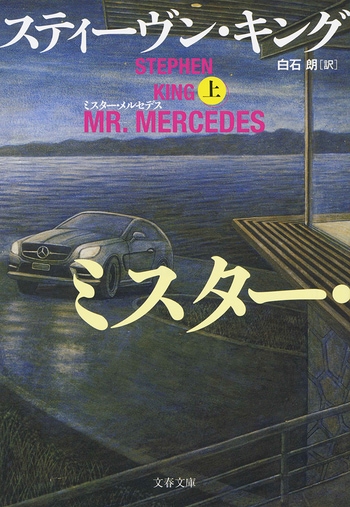探偵役と犯人の知恵比べといえば、現在のアメリカ・ミステリ界の第一人者であるジェフリー・ディーヴァーが得意としている構図だ。『ボーン・コレクター』(一九九七年)に始まったリンカーン・ライム・シリーズでは、四肢麻痺の元科学捜査官ライムが、天才的頭脳と実行力を持つ犯罪者たちと毎回渡り合うことになる(ライムが当初自殺願望を持っていた点はホッジズに似ているとも言える)。最近邦訳されたアメリカ・ミステリで言えば、ジョン・ヴァードン『数字を一つ思い浮かべろ』(二〇一〇年)やJ・D・バーカー『悪の猿』(二〇一七年)なども、優秀な探偵役と天才型犯人の対決の面白さをメインとする作品だった。
本書もその系列に連なっている作品だとも言える。ただし本書の場合、ホッジズは市警勤続四十年の敏腕刑事だったという設定で、実際、メルセデス・キラーからの手紙を分析するくだりでは長年の捜査官としての豊富な経験を窺(うかが)わせる老練さを見せるものの、ライムのような超人的頭脳の天才というわけではない。一方のメルセデス・キラーも、ホッジズへの手紙とオリヴィア・トレローニーへの手紙で文体を使い分けたり、メルセデスによる襲撃の際に身元を用心深く隠す工夫をしているなどの狡猾さを示してはいるけれども、ディーヴァーの作品に出てきた“ボーン・コレクター”“イリュージョニスト”“ウォッチメイカー”といった華麗なる犯罪者たちとは比較にならない。ホッジズを自殺に追いやろうとしてかえって奮起させてしまったのをはじめ幾度も失敗を繰り返しているし(そのせいで思わぬ方向に被害が拡大するあたりが余計にたちが悪いのだが)、チャットでホッジズに煽られて逆上するあたりは小物っぽさすら漂う。とはいえ、再び大量殺戮を企てるメルセデス・キラーと、それを阻止しようとするホッジズが、互いの行動を読んで先回りしようとするクライマックスの心理戦はスリル満点で、天才同士の対決ではないだけに身近なリアリティが漂う。また、不遇感を募らせ自尊心肥大に陥り、自身もろとも大勢の人間を巻き添えにして滅びようとする犯人像は、現実に世界中で見られるようになった犯罪者像を彷彿(ほうふつ)させるものがあり、老いても衰えないキングの作家的嗅覚の鋭さを示している。