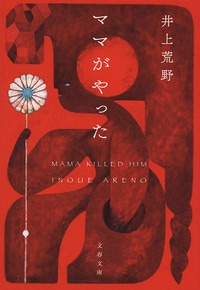
そう、ここには日常を生きることの綱渡りが描かれてある。一歩間違えば簡単に、人は殺したり殺されたりする情況へと入り込むのである。笑いのあとに突然噴出する暴力などを見ると、人はみな生まれながらの犯罪者ではないのかと思わせる恐怖がある。本書の装いは、脱力したユーモアとドタバタ劇が面白いクライム・コメディだが、本質的には倫理も正義もないアナーキーな不条理劇といえるだろう。とてつもない傑作である。
以下は、余談になる。でも、井上荒野の本質に関わる話でもある。
数年前、井上荒野と角田光代の両氏を山形の小説家講座にお招きしたことがある。そのとき、お互いの小説に対する感想をうかがったのだが、これがとても鋭かった。
井上氏は、ひとつの絵にたとえるなら角田光代は、“端から言葉でちょっとずつ構築していくタイプ”で、自分の“小説の世界観をものすごく確信している”“揺るぎない自信とエネルギーがあって”うらやましいというのである。その角田光代観が最も顕著にあらわれた“建築物”が、(これは僕の考えだが)本書と同じく二〇一六年一月に刊行された裁判小説『坂の途中の家』ではないかと思う。幼い娘を虐待死させた主婦の裁判を、裁判員に選ばれた主婦が見続けて判断を下す物語は、日常の細部の一つ一つを検証し続けて息詰まるほど。普通ならざっと玄関から入ってみて内側を見物して外に出ればいいのに、角田光代は玄関の扉の材料・壁・柱など個別に見ていかないと気が済まない。普段四二〇頁の“建築物”(小説)など数時間で見る(読む)ことができるのに、精緻な作りに魅せられて見る(読む)のに四日もかかってしまった。



















