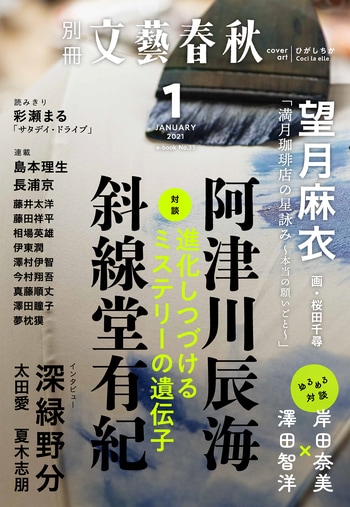2020年、ミステリ―好きを虜にした『透明人間は密室に潜む』と『楽園とは探偵の不在なり』。年末ランキングも席巻した二作の著者、阿津川辰海と斜線堂有紀は同世代にして同年デビュー。数多の名作ミステリーを血肉とし、新作を発表するごとに驚異的な飛躍を見せる二人の、初めての対談が実現した。それぞれのルーツから貴重な創作論、超ディープなビブリオバトルまで、本格ミステリーの新たな地平を切り開く二人の話は止まらない――。
※(*1)から(*6)まで、単語の後に註がついている箇所があります。数字をクリックすると最終ページの註一覧にとびますが、ブラウザのバックボタン(「←」)を押せば元の位置に戻れます。
阿津川 斜線堂さんの小説には“約束された破滅”があって、そこに向かって物語が駆動し、加速していく感覚がたまらないんですよね。私の最愛のノワール作家、ジム・トンプスンに感じるのと同じ感動を、斜線堂作品は味わわせてくれる。私は特に、斜線堂さんの『私が大好きな小説家を殺すまで』が好きなんですが、これなんて冒頭から破滅の予感に満ちていますし、『恋に至る病』も同様です。あと『コールミー・バイ・ノーネーム』は……。
斜線堂 うわあ、そんなに読んでくださっているんですか。ずっと「同時代に阿津川辰海が生きているという事実が大きすぎる」と公言してきた身にはありがたすぎて、震えます。
阿津川 いやいやいや(笑)。あの、今日は編集部から、存分に固有名詞を出し合いながら対談してくださいと言われていますし、せっかくなので、いろいろな作品の名前を挙げながらお話しさせて頂きますね。まず、斜線堂さんの『コールミー・バイ・ノーネーム』なんですが、これは大学生の世次愛が“女性を拾う”シーンから始まりますよね。私の好きなノワールの作家にチャールズ・ウィルフォードという人がいて、実は彼が『拾った女』(原題『Pick-Up』)というそのものずばりの作品を書いているんです。もちろん展開もテイストも何ら重なっていないですが、読み始めた瞬間のわくわく感、出だしから「この人はきっと私が期待する破滅の物語を見せてくれる!」と思わせてくれるところがそっくりなんです。
斜線堂 光栄すぎますね……。
阿津川 『楽園とは探偵の不在なり』の設定を知ったときも、「その設定で書くとか正気か!?」と思うと同時に、斜線堂さんがこの設定に踏み切ったということは……と昂りました。きっと斜線堂さんの新しい代表作になるだろうと。実際、本格ミステリーとして心惹かれたところがいくつもありました。主人公の青岸焦が色濃くまとっている、破滅に向かう者の影もよかったですね。
斜線堂 嬉しいです。
阿津川 そこで思い出したのが、ちょっと大げさかもしれませんが、鮎川哲也先生の『りら荘事件』です。私にとって、心の故郷みたいな作品のひとつなんですが、超連続殺人をやってのけているのに、一個一個の殺人にきちんと動機の仕掛けやトリックが用意されている。それがいちいち高密度なんですよ。『楽園とは探偵の不在なり』もそれぞれの殺人に仕掛けが施されていて、『りら荘』を読んだときの「すごい贅沢な作品を読んだ」という感覚がよみがえりました。もちろん、二作とも違った読み味になっているわけですが。
斜線堂 私が阿津川先生の『名探偵は噓をつかない』に感じたのがまさしくそれです! 『名探偵』は、最初から最後まで読者を楽しませようという気概がすごい。私はゼロ年代の新本格ミステリーが大好きなんですけど、『名探偵』を読んで以来、阿津川辰海こそ新本格の正統な後継者であり、敵う者はいないかもしれないという畏れとともに作品を追ってきました。

阿津川 ありがとうございます(笑)。
斜線堂 光文社の新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」(*1)でデビューされたとき、宣伝を見てすぐ「これは、私がものすごく好きなやつでは」と、発売直後に買いに走りました。勘は当たりましたね。本当に面白かった……。
私はミステリーという形態が、物語を楽しませる最良のかたちだと思っているのですが、阿津川作品は、そこに特殊状況を持ち込み、だからこそ生まれるロジックに抜群の納得感がある。展開も二転三転し、なおかつキャラクターが魅力的で、どの登場人物にも感情移入できる。続く二作目の『星詠師の記憶』もまた面白いんです。予言という非現実的なギミックをミステリーに組み込んでいるのに、読者に疑問を感じさせる余地を与えない完璧な構築をしていて、「この人は本当に天才なんだな」と衝撃を受けると同時に、阿津川先生と同年デビューだった私は、「このままだと置いていかれる」という焦りを感じました。そこから対抗心を燃やして書いたのが『楽園とは探偵の不在なり』なんです。
阿津川 いや、あの、顔が熱くなってきました。これゲームだったら完全に死亡フラグですよね。帰り道に事故に遭って、死ぬんじゃないでしょうか?
斜線堂 あはは(笑)。いやでも本当に、阿津川先生の作品の密度は尋常じゃない。「この一球にすべて込める」みたいな作り方ですよね。『透明人間は密室に潜む』に収録されている「第13号船室からの脱出」に出てくる脱出ゲームなんて、実際にあれで脱出ゲームを開催できるレベル。それを骨子として使いながら、別の軸のミステリーをやってみせる豪華さ。あれができるのが阿津川先生の強みであって、そのくらいでないといまのミステリーの最前線にはいられないのかという凄みを感じました。毎回読者に「すごいものを読んだ」という充実感を刻んでくれるのが阿津川先生の魅力です。