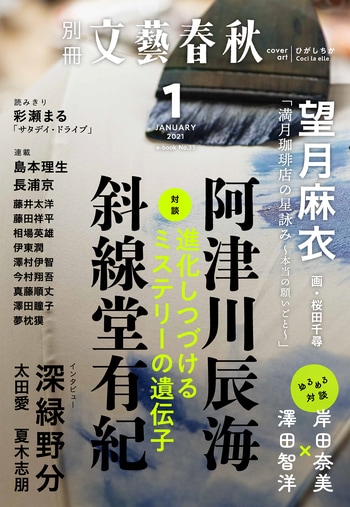二回戦・クリエイティブの極致を見せる小説家
阿津川 キングとブランド、一回戦はそれぞれ手堅いチョイスでしたね。それでは二回戦、斜線堂さんお願いします。
斜線堂 次はこちら、『崖っぷち』(フェルナンド・バジェホ/久野量一訳/松籟社)です。これは〈創造するラテンアメリカ〉というシリーズの一冊で、著者はコロンビア出身の作家です。舞台はコロンビアが一番荒れていた一九九九年で、主人公には兄弟が二十人くらいいるのですが、生活環境が悪すぎて、みんな薬物中毒や病に苦しみ、病気で死ぬか自殺するかしかないというある種の極限状況なんです。父親も肝臓がんで死にかけていて、主人公はそういった家族をひとりひとり看取っていく。
阿津川 なんて壮絶なんだ……。
斜線堂 あらすじを追うタイプの小説ではなくて、主人公の絶望をどこか軽やかに綴っていく、その文章のドライブ感こそが素晴らしいんです。父親を安楽死させたり、弟たちを看取ったりしているうちに、追い詰められた主人公は結局家から逃げ出してしまう。言葉にしてしまえばただそれだけの救いのない小説なのですが、著者はその物語をポップでユーモアに溢れた筆致で書いていて、読後感はまったく悪くないんです。この語りの軽やかさに私は舞城王太郎先生に近いものを感じました。絶望的な状況をエンターテインメントにしようとする気概に溢れていて、本当に絶望的なことからは距離を置かないと生きていけない、そのためにこの主人公には言葉が必要なのだということが切実に伝わってくるんです。
阿津川 これは絶対読みたいですね。帯の「拝啓、クソったれ世界様。」というコピーも最高です。
斜線堂 『崖っぷち』に出てくる人たちはみな、新しい年になればこの状況も何とかなるだろうと縋るように考えているけれど、結局その前にみんな死んでしまう。物語が進むにつれて、主人公は何も助けてくれない神様を憎んでいくのですが、憎悪を込めた激しいセリフの、そのひとつひとつがまた素晴らしい。そんな彼が父親を安楽死させてしまったときだけは、物凄く綺麗な言葉を使うんですよね。本当に悲しんでいるときに、彼は詩人になる。でも、その悲しみに取り込まれてしまいそうになったら、またポップな憎悪を吐き出すモードに切り替えて乗り切ろうとする。このままだと読者にこの底の無い悲しみが気づかれてしまうぞ、と言っているみたいに。彼は自分の内面を文章でコントロールしているんです。この感覚は間違いなく、読書でしか体験できないものだと思います。
阿津川 (冒頭数ページをその場で読みながら)……こんな素晴らしい本、どこで知ったんですか?
斜線堂 殆ど偶然なので、あんまり言いたくないんですが、高校時代に海外文学にはまって、アマゾンで次々買っていたらレコメンド欄が翻訳小説だらけになったことがあって……そこから知りました。当時の私は翻訳小説にどっぷりと浸かっていたので「ここに表示されている本、全部読んでやろう!」と。『崖っぷち』にもそのときに出会い、他の〈創造するラテンアメリカ〉シリーズの本もすべて買いました。このシリーズには“言葉で自分の現実に立ち向かう”タイプの小説がそろっていて、そのとき私が抱えていた「自分はこれからどうしたらいいんだろう」というありがちな自我の淀みを、ずいぶんなぐさめてもらいました。
阿津川 これは……刺さりまくりますね。最初の数ページを読んだだけで、間違いなく、私にとっても一番好きな類の小説だとわかります。
斜線堂 絶対に阿津川先生が好きだろうと思って持ってきました(笑)。
阿津川 よし、斜線堂さんが素晴らしい本をご紹介くださったので、私の二冊目はエドワード・ケアリーの『望楼館追想』(古屋美登里訳/文春文庫)でいきます! ケアリーは私が一番面白いと思っている現役作家のひとりで、これは、タイトル通り「望楼館」というマンションが舞台になっています。主人公はフランシス・オームという四十代くらいの、いつも白い手袋をつけている風変わりな男性で、彼は親の庇護を受けて暮らしながら自分で博物館を作っています。フランシスは“かつて人に愛された物”を集めていて、例えば子供が落としてその場に残されたおもちゃを拾ったら、「おもちゃのコンコルドの飛行機」とラベリングして収集する。それが彼にとってのこの世との縁になっているんです。
本の冒頭にはケアリー自身が描いたフランシスのイラストが載っています。彼はまず主人公となる男のイラストを描いて、この気味の悪い男はどのような人間なのか想像を膨らませてから小説を書き始めたんですね。次に出た『アルヴァとイルヴァ』、こちらはミニチュアの街で起こったことが、現実の街でもそっくりそのまま起こるというファンタジーで、そのミニチュアの街の写真も本に載っているのですが、それも自分で作っています。ケアリーは小説に絵や写真を取り入れながら“小説が好きな人のための小説”と呼ぶべき作品を毎回書いている作家なんですよ。いわばクリエイティブの極みですよね。

斜線堂 それはすごい……。
阿津川 『望楼館追想』の巻末にはフランシスの「愛の展示品」という付録まで付いていて、これは、「1 領収書 一点 2 使用済みの封筒(白) 一点……」といった収集品のリストになっているんです。初めて読んだとき本当に興奮して。本編には必要のない情報かもしれませんが、リストを眺めているだけでイメージが喚起されて、すごく楽しいんです。
もちろんストーリー自体も素晴らしく、大変壮大なところまで話が広がっていくのですが、最後はフランシスの物語としてきちんと収束するんです。同時にすべてを滅茶苦茶に破壊すらしてしまう……。このふたつが奇妙なかたちで同居しているところがまたユニークなんですよ。『望楼館追想』は本棚のいつでも手に取りやすい場所に置いてあって、いまでもよく読み返しています。
また、ケアリー作品は脇のキャラクターもすごく良くて、マダム・タッソーがろう人形館を立ち上げるまでを書いた『おちび』という作品では、パリ帰りの男が登場するのですが、彼はパリで履いていた靴に布袋をかけて履き続けているんです。地元の街路に靴を触れさせるのもいやだ、というわけです(笑)。彼にとって、その靴は思い出のパリを感じることのできる大切なものなんですね。物に対するフェティシズムが全編に溢れていて、『望楼館追想』の巻末リストもまさしくケアリーの物への偏愛を表しているのだと思います。
斜線堂 ああ、聞いたことがあると思ったら! 『おちび』、私も読みました! もしかしてあの自由に入ってくる挿絵は全部エドワード・ケアリー自身が描いたんですか!?
阿津川 そうなんです。あとケアリーは、デビュー作から一貫して“居場所を見つけられない人が居場所を見つけようとする話”を書いていて、そういう話に私はとても弱いんですよね。私は絵を描けませんし、仮に描けたとしてもケアリーのようになれる気はしません。逆立ちしても一生追いつけない。だからこそ私はケアリーが大好きなんです。