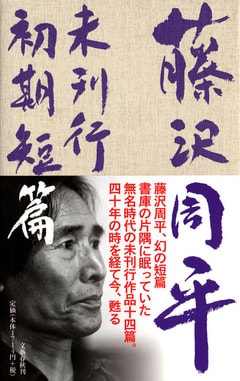3
「随筆九篇」としてまとめられたエッセイのなかに、長篇伝記小説『一茶』に言及している二篇がある。むろんここは小説『一茶』について論ずべき場所ではないが、二篇のエッセイによって示唆されたことについて少しだけ書いておきたい。
藤沢周平が一茶を書くと聞いたときから、喉に何かがつかえているような、すっと納得できないような思いが私にはあった。私の狭い了見は、藤沢『一茶』を読んで全面的にひっくり返るのだけれど、「喉のつかえ」とは、藤沢作品の端正さと一茶が合わないという勝手な思いこみから来ているものだったらしい。
藤沢自身が「小説『一茶』の背景」で、「一茶は、必ずしも私の好みではなかった」と書いていることを、私なりに勝手に忖度(そんたく)していた、ともいえる。
しかし「好みではなかった」という一行のすぐ後に、一茶の生活にふれたいくつかの文章を読んだ後で、しだいに一茶の全貌が見えてきた、といっている。「一茶は、多くの俳人の中で、私から見ればほとんど唯ひとりと言っていいほど、鮮明な人間の顔をみせて、たちあらわれてきた人物だった」。
一茶は弟から財産半分をむしりとった人間であり、義母や弟との争いは苛烈なものだった。その苛烈さは、「父の終焉日記」や「七番日記」とか「句帖」のなかで一茶自身がくわしく書いている。そういう一茶について藤沢はいう、「私の興味はむろん後半の部分、俗の人間としての一茶を書くことにあった」と。
とはいえ、一茶は生涯二万句以上の句を吐いた俳諧師でもある。十七字の言葉によって独自の世界を創造した人間でもある。それを無視できない、という意味のことを藤沢周平はつぶやくように書いてもいる。
小説『一茶』を読めば、親族と争って退かない「俗の人間」と俳諧師としての在り方が、絡みあいながら浮びあがってくるのを目の当りにするが、作家の工夫はひとかたならないものがあったはずだ。
おそらく一茶へのある種の共感がなければ、その絡みあいは描けない。しかし、「俗の人間」にべったりとくっつくような共感がもとよりあるわけではない。共感の距離のようなものが、じつにみごとに働いている。その距離感によって、一茶という凄味のある人間が立ち現われる。私はそんなふうに思った。
エッセイのなかで、北信濃柏原つまり一茶の故郷であり後半生を送ったその場所へ取材に行ったときのことが記されている。
《それにしても、信濃という言葉には、どうして人をいざなうような快いひびきがあるのだろうか。私は雪をかぶった信濃の山山を、車窓から飽きずに眺めながら、そう思った。そしてまったく突然に、一茶を書くことにしてよかったと思ったのである。》(「小説『一茶』の背景」)
小説『一茶』は柏原の中農の長男として生れた弥太郎(一茶)が、義母と折り合い悪く、十五歳で江戸に奉公に出される場面から始まっている。村はずれの桃の花咲くうつくしい丘の上で、父の弥五兵衛と別れるのである。
そんなに貧しくはない農家の長男が、農民であることに別れを告げ、何が待ち受けているかわからない都市に向う。その場面は父子の思いを伝えるように、ていねいに描かれている。一茶は、百姓になれず、かといって町民に徹することもできず、俳諧師という奇妙な存在となって、結局は郷里に戻ることを選んだ。そういう人間に、作家は距離感のある共感をいだいていると私は思った。