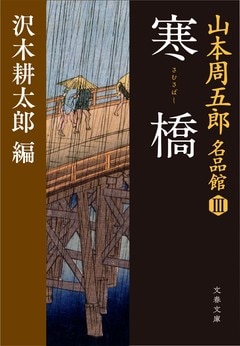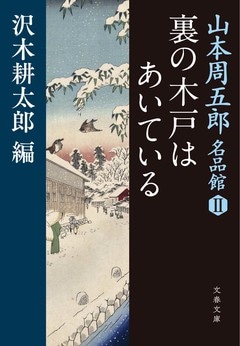ある日、深川一帯が嵐に見舞われる。風が吹き、水が出る。そして、徐々に水位が上がってくる。
かつて私が子供だった頃、戦後の東京の下町でも、近くの川が氾濫し、水が出るということがあった。私の家でも、大急ぎで畳を上げ、その上に大事なものを載せると、舟に乗って近所の風呂屋に避難したりした。その風呂屋には天井の高い浴場の上に大広間があったからだ。それから水が引くまでの数日間をそこで過ごしたが、子供にとっては、何かお祭り騒ぎのような楽しさがあった。
だが、このときの深川は、その域を超え、すごい勢いで水位が増してくる。やがて屋根の上までのぼって避難を続けなくてはならなくなるのだ。
その前に、みんなは逃げるが、姉さん格のおひろとおぶんだけは逃げようとしない。おひろは旅に出ている女あるじから家を任せられているためだが、おぶんが逃げないのは、もしかしたら、という思いがあるからだ。
――もしかしたら、あの人が助けに来てくれるのではないか。
だが、その思いを打ち砕くようなものとして、おひろの口癖が反響する。
《「どんなにしんじつ想いあう仲でも、きれいで楽しいのはほんの僅かなあいだよ、露の干ぬまの朝顔、ほんのいっときのことなのよ」》
本当に、二人の仲は「つゆのひぬま」のあいだだけのことなのだろうか。いや、そうではないと、証明できるのだろうか……。
最後に、主人公が、おぶんからおひろにするりと替わるような気がする。それが余韻の深さをさらに増していくように思われる。